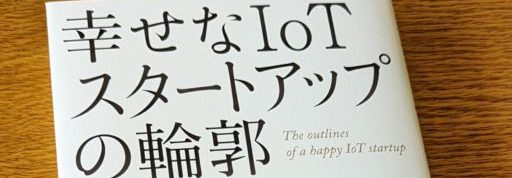セラノスにはスタートアップあるあるが詰まっていた

『BAD BLOOD』を読んだ。
一時は世界最大級のユニコーン企業となったセラノスが、実際は嘘と捏造にまみれた会社である、ということを告発したウォール・ストリートジャーナルの記者の著作だ。
実際の告発から凋落が起こったタイミングを時系列で思い起こすと、私はアメリカから日本に移り、スタートアップで事業立ち上げに取り組んでいたタイミングで正直セラノスについてはネットの記事でチラッと読んで「マジかよ」と思った程度だったが、シリコンバレーでのエリザベス・ホームズの持ち上げられっぷりはよく見ていたのでその分大きな衝撃は感じた。(しかし当時は自分のことが忙しかったからすっかり忘れていたw)
この本には元社員や関係者たちの告白とそれを入手した著者が記事の公開までこぎつける過程での奮闘が克明に記されている。
極めてショッキングな話が次々と並ぶが、一方で冷静に足を止めると
「これって程度の差こそあれほとんどのスタートアップでセラノスと似たり寄ったりのことが起きているんじゃない?」
と思い当たる。
ただ皆セラノスほどの資金は集めてないし、セラノスほどメディアにも注目されてないし、セラノスほど大物は関わってないし、セラノスほど訴訟にまみれていないので、結果、ネタとしてエキサイティングさで劣る。それだけの話だ。
いくつか思ったところを書いていこう。
『ハッタリ』
初期のスタートアップにとっては多少のハッタリで資金調達をしてくることはもはや常識と言ってもよいほどの悪習だ。
いや、あながちに悪とは言い切れない。
そのハッタリを実際に形にして辻褄を合わせてくるやつは「少ないが確実にいる」からだ。
投資家もそれをわかった上でのチキンレースをしている部分は否めない。
でもそれはあくまで「プロの起業家」と「プロの投資家」の間での美学あるゲームであって、素人同士がやったらそれは詐欺でしかない。
『関係性がよくわからない株主』
どこの株主の名簿を見ても関係性がよくわからない株主がひとりふたりくらいは入っているものだ。
それ自体は構わない。
「事業のことはよくわからないけど資金援助の形で応援するよ!」という気持ちは当然あって良いものだ。
しかし、そのひとりふたりが誰もが知っているような大物の場合、大きく話が変わってくる。
『一人大物が食いつくとその後の金が集まりやすくなる』
からだ。セラノスのケースでは初期から超大物が株主に名を連ねていた。
仮に彼らが「ちょっとした余剰の投資資金で若い起業家を応援した」だけだとしても、その株主名簿を見た人たちは「〇〇氏が責任持って支援している事業なら彼女(エリザベス)の言っていることは本当に違いない」と勝手に勘繰ってしまう。
実際問題、プロのベンチャーキャピタリストであってもきちんとしたデューデリジェンスを完全に自力で行えるケースは少ないように思う。テックベンチャーはなおさらのこと。誰かの助言であったり、過去のデータであったり、何かしらの手がかりを元にDDを成立させる。
そのような場合に既存株主リスト、あるいはそのシリーズを取り仕切るリードインベスターの「名前」はひとつのミスリードの元になってしまうことがある。
『経営者が優秀な部下の言うことを聞かず、どこかの有名な金持ちの言うことを聞いている』
部下はその分野のスペシャリストではあるが、経営者ではない。
特に社会人経験の乏しい科学者やエンジニアは政治や金の部分の疎さは否定できない。逆に有名な金持ちは大抵の場合で金持ちになるだけの理由がある。ビジネスにも政治にも通じているし利益に聡い。
経営者はどうしても部下に対して「(全体像がわかってないなぁ)」と思ってしまうことがある。その際に、逆に俯瞰しか見てない第三者の意見に流れてしまうことは、残念だがある。
しかし部下はその第三者のことを知らないし、当然尊敬もしていないし、頼りにもしていない。
自分が所属する組織のトップが自分の方を向かずにどこかに存在する何かの言いなりになっているような感覚を持ったら、当然気持ちは離れる。
『情報の分断』
セラノスは確かに前人未到の画期的な発明に向かってチャレンジしたが、あれだけの資金を集めて、優秀な人員を集めたのだから「もうちょっと惜しいところまで来ててよかったんじゃないの?」と思った人も多いのではないだろうか。(実際は彼らの検査装置は箸にも棒にもかからないレベルだったわけだが)
14億ドル以上の資金があって、600人以上の社員がいて、10年近くの年月があったら、どんな大発明でも可能なのではないかとすら思える。
しかしそれができなかった理由のひとつが徹底した情報の分断ではないかと読んでいて思った。
秘匿性の高い技術や機能について一部の人間にしか明かさないという措置はよくある話だ。Appleでも「製品仕様はスティーブ・ジョブズかジョナサン・アイブに聞いてくれ。そもそもおれたちは知らされてないから」というのは常識だったらしい。
しかし、全ての部門が横連携できないような体制を作ってしまっては開発が成り立つわけがない。おそらくそれぞれのメンバーは「とりあえずいい給料もらえてるし目の前のことやってればいいや」くらいに思っていたのではないだろうか。結果、全く使い物にならないシステムを作っていることについても皆「どうでもいい」「興味なし」「ていうか全体像よくわかんないし」ということになっていたのではないだろうか。
アメリカ人と分業
アメリカ人は分業が好きだなぁと思ったことがある。
自分の担当範囲をハッキリさせることで、責任、人事査定、必要スキル、タスク状況=プライベートの確保、などが明確になるからだろう。これはチームがチームとして有機的に機能しなくなるリスクを常に孕んでいて、それは例えばアンディグローブが日本の半導体が米国を脅かしていた時期にそのことを強く指摘している(とはいえ文化だから残り続けている)
『トップが現状をわかっていない、あるいは理解しようとしない』
組織の横の繋がりを分断しても回る組織はある。それは中央集権的な組織だ。トップが優秀であれば回る。大変だけど。
しかし、例えばテック企業なのにトップが非エンジニアである場合などは側近の存在(多くはCTO)が重要になる。側近がまともであり、トップとの信頼関係が固ければこの問題は十分に補完できる。
しかし「トップが現状を理解していない」「側近も理解していない」「トップも側近もまともではない」までが揃ってしまったらもはやどうにもならない。お手上げだ。
『どこかでしてきた約束』
マイルストーンにないスケジュールで急かされる、という経験がある人は少なくはないのでは。
経営者がセールスを兼ねている会社では「どこかで勝手に約束してくる」ということがある。ビジネスチャンスを掴むことにやっきになった結果であって、そう邪険にはできない。
本来はその情報をチームに共有すべきである。そうすればチームも渋々ながら納得する。しかし、それを言わない場合、信頼関係は損なわれる。社員は奴隷ではないのだ。
『縁故幹部』
幹部の選出には信頼関係が重要だ。それはどこの企業でも変わらない。
しかし信頼関係の使い方は「意見のぶつかり合いを恐れない」という使い方をするべきだ。
セラノスではCOOが恋人、幹部はろくな実務経験がないエリザベスの弟、その友人、というように何かを生産的に積み上げることができるような選出がされていなかった。そして本来は「お兄さん役」あるいは「お父さん役」として機能しなければならない取締役会もエリザベスと個人的な関係があるメンバーで固められ、議決権は90%以上をエリザベスが握っている状況が長く続いていた。これは極めて悲劇的な状況だ。
『学歴だけで実務経験が薄い人間が重用される』
学位というのは結構使える飛び道具だ。実際シリコンバレーで繰り広げられるスタートアップのピッチ資料などには大抵の場合でみなビックリするくらい名門大学出身者の名前ばかりが並ぶ。しかしそんなことが本質的な話ではないことはみんな知っている。知っているのに何故かその風潮が絶えないのは一種の忖度なのだろうか。
学歴は使えるけどこけおどしでしかない。例えばよく知られている日本の学歴ハックに「東大卒の肩書きが欲しいなら大学院で入れば良い」というのがある。学部時代の成績と論文と面接で十分評価してもらうことができる。一発勝負の入試よりもよっぽど勝算が高い。
『お飾りのコンサルに高報酬』
幹部以外が会社の会計資料を見ることはなかなかない、が、ないではない。
支払い先の履歴の中にとある個人名。ググってみると非常に大物あるいは顔役であることがわかる。
とはいえ社内で名前を聞いたことがないし、どういう役割かわからない。
それとなく問いただしていくと「〇〇についてアドバイスをもらってる」「ん?〇〇ってごく最近の話だよね(一年前から払い続けてることになってるけど。。。)」
要するにお飾りなのだがそこにエンジニア数名雇えるレベルの金が流れていたりした日にはげんなりすること間違いなしだ。
『突如いなくなる退職者』
セキュリティが厳しい会社では退職者がミーティングルームで退職の意思を告げるあるいは解雇を宣告された後にデスクに戻ることなく会社を後にするということはある。これは一般デスクに戻った後に機密情報の持ち出しや情報漏洩のリスクを防ぐためだ。
という一般論以外に、「会社のことを周囲に悪く言わせないため」だったり「強引な解雇なので何かしら報復行為に出ないように」というような、要するに円満な退職ではないことによるマイナスの余波を防ぐための手段、というケースが実際には少なくないように思う。
退職者が、周囲のメンバーと何もリスクが無かったにも関わらず挨拶すらせずに唐突にいなくなるのは、大抵がこのパターンだ。ヤバい会社の印である。
『やめる会社の株式欲しい?』
これは非常に深刻な話だが、一般論として株式を所有していた幹部を会社側からのアクションで放逐する場合、会社としては意地でも株を戻させたい。要するにこれも円満退社ではないパターンなのだから、外部に私怨を持たれかねない株主がいる状況は経営者からしたら例えそれが少数株だとしても寝付きが悪いものだ。
しかし放逐された側からすると「なぜ強引に放逐された上に、さらにお前らの要望を聞かなければならないんだ」となるのは当然だ。しかし契約書を盾にしたり何かしら法的手段に訴えて会社側が強硬な回収に動くケースは少なくない。
セラノスではアヴィというNextとAppleでジョブズの側近を務めたベテランがこの憂き目に合うが、弁護士に相談した時に言われてしまうのが「その会社のこと有望だと思ってるか?苦労してまで保持する価値がある株式か?」という趣旨のセリフ。
当然未練などない、と多くの人が思うのではないだろうか。
実際アヴィもそうした。
『真っ当なことを言うと追い出される』
イアンのくだりは読んでいて本当に気持ちが重くなる。経験豊富なベテラン科学者がセラノスの検査機器の性能に待ったをかけたら「非協力的」とみなされて窓際に追いやられ鬱になったのちに、、、という話だ。
優秀な科学者やエンジニアは「真っ当なこと」を言うのが得意である。それはもはや生命の神秘と言っても良いほど万国共通で一貫している。
多くの初期のスタートアップにおいて「壮大なビジョン」と「貧弱な現実」のギャップはあまりに大きい。
そんなことはみんな知っている。
しかしそれでも熱狂とともにそれを推し進め続ける。
振り返ってはいけない、迷ってもいけない。とにかく進むのだ。
そんな状況で「真っ当なこと」を取り出した批判の類は当然歓迎されない。明晰な経営者であれば「指摘には感謝した上で、あえて進む」「回避策を考えて、進むことはやめない」「この一線を超えることはできないので止める」というような相応の判断を下すことができるはずだ。
しかしマズい状況にある経営者および会社においてはそれを無視したり、踏みつけたり、横に退けて何もなかったかのように先に進む。
当然優秀な科学者やエンジニアの言うことも万能ではない。彼らの予測が外れ大成功を成し遂げるスタートアップもある。しかし多くの場合は「誰かがハマったことがある落とし穴に懲りもせずまたハマる」のが関の山だ。
『次々と分不相応な賞を受賞』
別のnoteでも書いたが、ヤバい状況にある会社のヤバさが実際に公になるまでには数年の時間を要することが多い。それはセラノスも例外ではなかったし、むしろそういう会社の方がほとんどだ。
したがって仮に何か大きな致命的疾患を抱えていたとしても、しばしの余命までの間は「今をときめくスタートアップ」であり続けることが可能である。
当然賞を受けることは名誉なことだ。選んでくれた人たちの期待も真摯に受け止めるべきだし、ステークホルダーたちも喜んでくれるに違いない。
しかし分不相応なものを受け続けることは別の弊害を生む。
「本人が現在位置を見失ってしまうこと」だ。
これ自体が極めて深刻な死に至る病である。